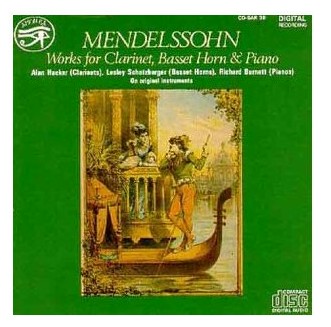 さて、今日の1枚は、メンデルスゾーンのクラリネット&バセットホルン&ピ
アノのための作品集。6月5日に紹介した田部京子のピアノ・ソロの無言歌集
の曲と結構重複している。しかし、楽器が全然違うので雰囲気も全然違う。
さて、今日の1枚は、メンデルスゾーンのクラリネット&バセットホルン&ピ
アノのための作品集。6月5日に紹介した田部京子のピアノ・ソロの無言歌集
の曲と結構重複している。しかし、楽器が全然違うので雰囲気も全然違う。
の
た
め
の
邪
魔
な
広
告
よ け ス ペ ー ス で す。
2009年6月30日(火)
<<授業アンケート>>
昼過ぎに出勤。郵便ポストに、昨日に引き続き、アメリカ数学会からの
論文レビューの依頼が来ていた。しばし眩暈。これから2ヶ月が猛烈に忙しく
なるっていう時に、2ヶ月期限の仕事が2つも来るかよ?!と呆然。
まあ、一応その辺に放置。
研究室こそこそ昼食の後、13時から14時半まで、経済学部、 経営学部のCプログラミングの授業。今日の出席者は元気な2回生3人組と、 久々登場の4回生1名。引き続き14時40分から16時10分まで、数理科 学科2回生の群論の講義。本日最後の15分は、お上から指令に従って授業ア ンケートを行う。
今日の群論の講義の出席者はざっくり60名弱で、アンケート提出者は3 0名弱。授業は「まずまず分かる」または「分かったような分からないような」 と答えたものと、「あまり分からない」または「全然わからない」と答えたもの が半数ずつ。ざっくり推計すると、60名弱のうち、10数名は何とか理解して おり、さらに10数名はぼんやりとは理解しており、あとの30名弱はかなり 苦労している。これだけ一所懸命教えてるのに、30名弱がそんな状態かよ、 とちょっとガックリくる。自由記述欄には、授業を比較的良く理解している グループから、板書と説明が速すぎてついていくのが大変、との意見が複数あ り。うーむ。
去年までは4〜5週分の話を15回に引き伸ばしてチンタラやってくよう なスカスカの講義しか担当したことがないけど、今年からいきなり25週分の 話を15週でやれ!みたな講座を担当したから、どうしても沢山書いて沢山喋っ て、、、という風になってしまう。しかも内容が群論だから毎回新しい概念の 洪水で、そうなると同じ事を具体例で計算して見せたり、こまめに復習したり ということもやっていかないと、「誰一人何も理解していない教室」という荒 涼とした風景が広がることとなる。またしても、うーむ。 なかなか難しいものである。
その後、群論の定期試験問題を事務に提出してから、帰宅。 夜も少し数学。
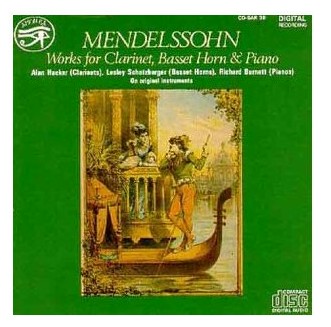 さて、今日の1枚は、メンデルスゾーンのクラリネット&バセットホルン&ピ
アノのための作品集。6月5日に紹介した田部京子のピアノ・ソロの無言歌集
の曲と結構重複している。しかし、楽器が全然違うので雰囲気も全然違う。
さて、今日の1枚は、メンデルスゾーンのクラリネット&バセットホルン&ピ
アノのための作品集。6月5日に紹介した田部京子のピアノ・ソロの無言歌集
の曲と結構重複している。しかし、楽器が全然違うので雰囲気も全然違う。
バセットホルンはバスクラリネットともいうクラリネットの仲間で、かな り低い音まで出る。少し前にゲーテ・クラリネット奏者氏が「バスクラ、買い ました!」と自慢していて、小さなコンサートで一度演奏したそうだが、残念な がら講義と重なっていて聴きに行けなかった。その後一向に人前で演奏する話 を聞かない。
このCDで使われているピアノは、最近の古楽器ブームでよく演奏されてい るフォルテピアノという現代のピアノの前身らしく、まあ、それなりの味があっ て良いのだが、音の伸びが悪く、ピンシャン、ピンシャンと玩具のピアノのよ うにも聞こえる。そういえばクラリネットもバスクラも、19世紀製の古楽器 を使っている。私としては、別に古楽器でなくてもいいんだけどね。
ジャケットのデザインは、昨日のスカルラッティのものと雰囲気は似てるけ ど、文字の書体に変化をつけている所が良いし、背景の抹茶色も私好みだし、 誰が描いたのか知らないけど絵も悪くない。
船の男:「それで、あの先生の群論の講義ってのが、板書の字は汚いし、 書くのも喋るのもメチャクチャ速いし、もう大変なんよ。」
ベランダの女:「そうなの。で、講義で聞き損ねた分を後で勉強できるよ うにって、レジュメか何か配ってもらってないの?」
船の男:「え?先生はレジュメは配ってるけど、授業中は全然使わないし、 何ページのどこを見ておけって事も言わないから、何のために配ってるのか 意味がわかんない。俺は全然見てないよ。」
ベランダの女:「馬鹿ねえ、貴方。レジュメや教科書を独力で読むの大変 だから、あらかじめ授業で概要やポイントを教えてもらうのよ。そうやってし て、授業の復習でレジュメとノートを見比べて読んだら、うんと理解しやす いじゃないの。」
船の男:「へーえ、そんな勉強の仕方があったのか。姐さん、ずいぶん気
の利いたこと言うねえ。」
2009年6月29日(月)
<<例外条項>>
昨夜は一晩じゅう数学を考える夢を見てうなされていた。もっとも、「数学を
考える夢」であって「夢の中で数学を考えて」いたのではないためか、特に
目だった進展はなし。
午前中は自宅で野暮用。ラクト山科で昼食用のパンを買って、昼過ぎに出 勤。昨日ようやく論文レビューの仕事から解放されたばかりだけど、アメリカ 数学会からの論文レビューの依頼が来ていた。とりあえず放置。自宅で原稿を作っておいた定期 試験問題を完成させ、明日の授業のプリントを印刷し、就職課(カタカナかぶ れのRitsでは「キャリア・オフィス」という)から来た研究室の学生の進路調 査票を記入し、来月末の親和会宴会の申し込みをし、といった雑用を片付け、 14時半から16時過ぎまで卒研ゼミA (可換環論・代数幾何学)。今週から テキストを変えてみたY君は、まずまず好調な再出発。
ゼミ終了後、もうひとりのゼミ生A 君の進路相談的な雑談をしているうち に、次のゼミ生が入ってきた。16時半から18時半ごろまで卒研ゼミB (初等整数論)。ある級数の収束性の証明に梃子摺って、どうやら来週の (私の!)宿題になりそうだなと困っていたところ、O君がうまい解答を思い ついてくれて何とか解決。こういうのは結構ゼミらしい雰囲気で、楽しい。
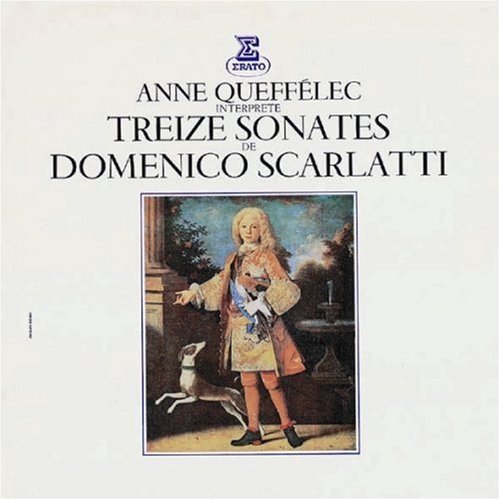 さて、今日の1枚は、アンヌ・ケフェレックが22歳だった頃の初々しいピア
ノで「スカルラッティー、ピアノ・ソナタ集」。スカルラッティーの時代だか
ら、もともとはチェンバロ曲なんだろうけど、ピアノで聴いても大変よろしく、
私のお気に入りCDのひとつである。
さて、今日の1枚は、アンヌ・ケフェレックが22歳だった頃の初々しいピア
ノで「スカルラッティー、ピアノ・ソナタ集」。スカルラッティーの時代だか
ら、もともとはチェンバロ曲なんだろうけど、ピアノで聴いても大変よろしく、
私のお気に入りCDのひとつである。
この絵は若い頃のスカルラッティーの肖像かも知れないけど、詳細は不明。 まあ、私はこういう古色蒼然とした絵には興味は無いし。大体、この人物のわ ざとらしいポーズのとり方と、とってつけたような犬のジャンプは何なのだ? と言いたい。肖像画の大きさ、位置、背景の白、(ちょっと単調な感じが気に なるけど)タイトルの文字。いずれもまずまず無難にすっきりと纏まっている けれど、それにしても退屈なジャケットである。同じスカルラッティーのCDで も、6月27日に紹介した「右半分は理解不能な世界」や、6月23日に紹介 した「物陰に潜むくノ一」のように、トンデモ系として楽しむことも難しい。
そういえば、金曜日の不滅のオジサン会合の写真を仲間うちだけにネット
で配布したら、欠席者のひとりのオジサンが「楽しそうだけど、これだけオジサンが
集まるとちょっと気持ち悪い」というような感想のメールを流していた。同感
である。オジサン嫌いの私も一応「オジサンになる前から友人だったオジサン
は除外する」という例外条項を設けてはいるが、
オジサンは群集の中で気配を殺して単独行動に努めるべきであって、
嬉しそうな顔して群れるような見苦しい真似は人目を忍んで行う
ぐらいにしてもバチは当らないかもね。
2009年6月28日(日)
<<カミキリムシ>>
カンカン照りの夏日。本日とりあえず、研究日。昼前から論文レビュー(その
4)の執筆開始。昼頃は麦藁帽子にサングラスのいでたちで自転車に乗って、
山科区内のスーパーに買い物に出る。ラクト山科で、情報理工学部の先生が小
学生ぐらいの息子を連れて歩いていた。昼食後、またレビューに取り組む。原
稿がほぼ完成したところで、夕方。先週さぼったラクト山科のスポーツクラブ
へ。
通り道の公園で猫がカミキリムシとじゃれていたので、しばし観察。最後 は頭を低く構えてじっと見てるだけで、なかなか追おうとしないので、「こら! ちゃんと気合い入れて捕まえんかよ!」って声を掛けたら、逃げていった。 黙って最後まで観察すべきだったのだが、先を急いでいたので、つい余計なこ とをしてしまった。まあ、私は虫にはあまり興味がないのだが、山科在住 通算22年にして初めてカミキリムシにお目にかかり、ちょっと感激。
私の子供の頃、私以外の小学校低学年ぐらいの男の子は、モンシロチョウ などを見ると、必ず被っている野球帽を虫取り網の代わりにして夢中で追いかけ るという習性を持っていた。割合月並みだったモンシロチョウならともかく、 アゲハチョウぐらいになると彼らの興奮ぶりはもうタダモノではなくなる。そ れで池に落ちたり、車にはねられたりする子供もいた。
チョウだって、そんな洟垂れ小僧にいちいち捕まってたのでは生活が成り 立たないので、ひらひら、ひらひらと、右に左に上に下にと巧みに逃げる。そ の動きはまさに複雑系というか文脈自由文法というか、数理科学科の教室会議 の議論を可視化するとあんな風になるのではないかと思う。
チョウを追う男の子は、大抵は逃げられて悔しそうにするが、たまにう まく捕まえることができると、目を輝かせて「高山、捕まえたぞ!」って自慢 するのだった。それ、ウチに持って帰って佃煮にして食べるっていうなら話は 別だけど、そんなの捕まえてどうするんだよ?どいつもこいつも変な奴らだな と思っていたものである。
さて、猫を逃がしてからは先を急ぎ、三条通りをラクトに向かっている途 中、クリーニング店の前で数理科学科の学生男女2人組と すれ違った。この二人には以前烏丸御池の路上でもすれ違ったような気がする。
夜はレビュー原稿を仕上げて、メールで送る。やれやれ、これで昨年9月 から滞っていた仕事が全て片付いた。その後も少し、数学。
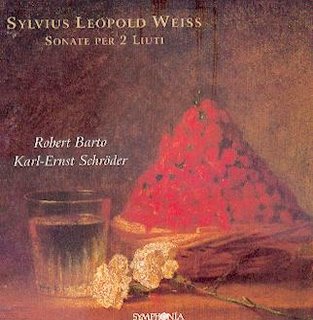 さて、今日の1枚は、J.S.バッハと同時代に活躍したシルヴィウス・レオポル
ド・ヴァイスの「2本のリュートのためのソナタ」。このCDひとつでヴァイス
のファンになり、彼が書いたリュート曲をいくつか聴いてみたけど、今のとこ
ろこの曲が一番良い。
さて、今日の1枚は、J.S.バッハと同時代に活躍したシルヴィウス・レオポル
ド・ヴァイスの「2本のリュートのためのソナタ」。このCDひとつでヴァイス
のファンになり、彼が書いたリュート曲をいくつか聴いてみたけど、今のとこ
ろこの曲が一番良い。
ジャケットの絵は18世紀に活躍した画家 Jean Siméon Chardinの
"Le pannier de fraises des bois" (野いちごの籠)という作品。
野いちごよりも、水の入ったコップのところが気に入っている。何よりも、こ
の曲の雰囲気に似合った奥ゆかしい感じがよろしく、この曲を知らない人に
「それはどんな曲か?」と聞かれたら、「この絵のような曲だ」と答えれば
良いところが、とっても便利である。まあ、誰もそんな質問をしてこないけどね。
2009年6月27日(土)
<<不滅のオジサンたち>>
昨日は昼過ぎに新幹線で東京へ。車中はヨーロッパ数学会から依頼された論文
レビュー(その4)の分厚い論文を読み飛ばす。お茶の水のビジネスホテルに
チェックインしてからも、もう少し読み続け、一応一通り目を通した。あとは
レビュー書きを残すのみ。
夕方は新橋に繰り出し、会社員時代の同期の人達と某中華料理店で飲み、 最後は新橋駅前広場のSL の前で「オジサンは不滅です!」と言わんばかりの 怪気炎漂う記念写真を撮って、ひとまず解散。JR秋葉原まで一緒だった友人と 閉店間際のSbuxに入り、22時半にSbuxを追い出されてからは、店の前で立ち 話。ふと時計を見たらもう零時を過ぎているので、近い将来の再会を誓い合っ て再びJRでお茶の水まで行き、ホテルに戻る。
今朝は、二日酔い気味の少し重い体をひきずって新幹線に乗り、車中でド イツ語寺子屋の予習。昼過ぎに京都着。一旦自宅に帰ってから、今度は寺子屋 塾へ。麦藁帽子と悪太郎サングラスのいでたちを見て、クラスメートの一人が 「高山さん、亡くなった父とそっくりで懐かしいです。父はさらに甚平を着て 下駄を履いてその辺をうろうろしてました」と。うーむ、私は一体どういうリ アクションを返せばよいのか?結局、私は甚平が大嫌いなので、「甚平とは、 すごいですね」という控えめなリアクションにとどめる。
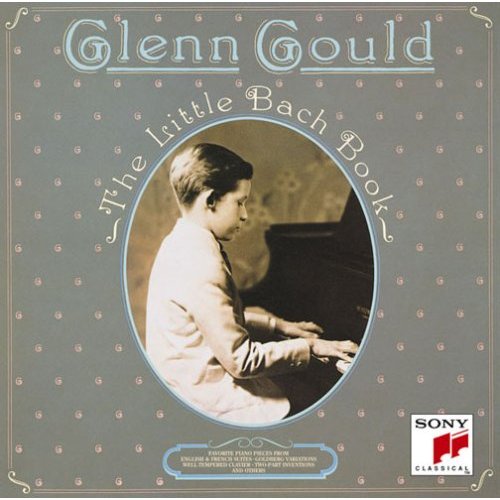 さて、今日の1枚は、マイケル・ジャクソンと同じく50歳で亡くなった
グレン・グールドの"The Little Bach Book".
J. S. バッハのピアノ曲の魅力の真髄が手っ取りわかる、選りすぐりの20曲。
さて、今日の1枚は、マイケル・ジャクソンと同じく50歳で亡くなった
グレン・グールドの"The Little Bach Book".
J. S. バッハのピアノ曲の魅力の真髄が手っ取りわかる、選りすぐりの20曲。
このジャケット、古いアルバムみたいなレトロな感じはいいのだけど、 "Glenn Gould"の2つの"G"の文字が、オジサンの鼻毛のように思えてちょっと気持ち 悪いのだが、それは昨日オジサンの街新橋で飲んだからであって、またいつも の静かな生活に戻ったら、何とも思わなくなるかと思う。
ところで、20代の頃は、夜、布団に入って寝入ろうとすると、ライフル銃 か何かで遠くの標的を狙う自分のイメージが浮かんで来た。別に意識してそう しようとしたのではなく、何となく思い浮かんでくるのである。毎日のように そういうイメージを思い浮かべていると、次第に狙っている標的のイメージが 詳細化されてくるのだが、人間や動物を傷つけるのは可哀想だし、物を標的に したら今度は器物損害罪になってしまうよな、というようなことを考え出し、最 後にはライフル銃のイメージは思い浮かばなくなった。
その後、長い間、寝る前は布団の中で目をつぶって数学を考えたり、音楽 が勝手に頭の中を渦巻いたり、あの野郎も余計なことをしてくれたものだ とブラックリストの更新作業を行ったりと、ごく平凡な就寝前のひとときを 過ごしていた。
しかし、最近は寝る前に、ピストルで自分の頭を打ち抜こうとしている自 分のイメージが思う浮かんでくるようになって、我ながら半ば呆れている。 弾丸が卵の殻を破るように頭蓋骨を突き破り、床に落とした豆腐のように脳味 噌が崩れ、高地完熟バナナのような脳幹を打ち抜いて心肺機能停止。やれやれ、 これでぐっすり眠れるわい、と。こうやって毎晩、数回から十数回「頭を打ち 抜いて」みるとようやく気分が落ち着くとみえて、そのまま寝付いてしまうよ うである。
こういう、寝る前に不意に湧いてくるイメージが何を意味しているのかは、
よくわからない。まさか、グレン・グールドもマイケル・ジャクソンも50歳
で亡くなったことだし、ここはひとつ、マイケルと同い年の私も何とかせにゃ
ならんなとかいう風に無意識に考えてる訳じゃないだろうけどね。
2009年6月25日(木)
<<冤罪事件>>
研究日。午前中は自宅で某文献をひっくり返し、午後は京大数学教室の図書室
でうんうん考える。すこし進展があった。でもまだまだ道は遠いな、と。京大
の帰りは、JEUGIA三条本店を偵察しCDを購入。夜はももう少し数学。
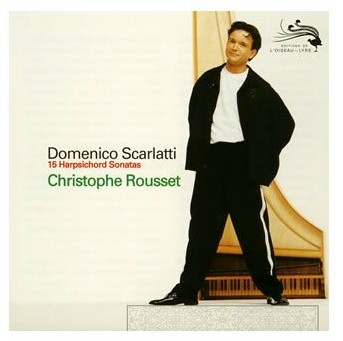 さて、今日の1枚は、数週間にわたる偵察・調査活動の末に、本日ようやく購
入したスカルラッティー「チェンバロ・ソナタ集」。「ソナタ・ハ長調
Kk.461」「ソナタ・ホ短調 Kk.531」云々という退屈極まりない符丁のような
タイトルが15曲分並んでいる。この時代の作曲家達は、曲への思い入れを込
めたタイトルを付けようという発想は無く、楽曲職人としてただただ一曲一曲
を丹精込めて作っていただけなのかもね。勿論、退屈なのは曲のタイトルだけ
で、中身はかなりスリリングな超絶技巧のスカルラッティー・ワールドが展開
されている。
さて、今日の1枚は、数週間にわたる偵察・調査活動の末に、本日ようやく購
入したスカルラッティー「チェンバロ・ソナタ集」。「ソナタ・ハ長調
Kk.461」「ソナタ・ホ短調 Kk.531」云々という退屈極まりない符丁のような
タイトルが15曲分並んでいる。この時代の作曲家達は、曲への思い入れを込
めたタイトルを付けようという発想は無く、楽曲職人としてただただ一曲一曲
を丹精込めて作っていただけなのかもね。勿論、退屈なのは曲のタイトルだけ
で、中身はかなりスリリングな超絶技巧のスカルラッティー・ワールドが展開
されている。
チェンバロを弾いてるのはクリストフ・ルセという人。チェンバロ弾いて るだけでは飽き足らないのか、最近はご多分に漏れず指揮者業にも精を出して いるようである。マッチョやねえ。大体このジャケットの写真は何なんだ?体 育館の壇上で竹刀を持って仁王立ちしている生活指導係の体育の先生みたいじゃ ないか。あれ?よく見ると、チェンバロがひっくり返ってる。 左半分は、背景 や文字の色など綺麗に纏まっているけど、右半分はもう私には理解不能な世界 なので、これ以上の論評は控えることにする。
それにしても、中学高校の体育教師たちにはずいぶんとっちめられたな。 私の頃は竹刀振り回している先生は居なかったけど、ラジオ体操で皆が右手挙 げているのに一人だけ左手を挙げていたとか、上体回しの動きが周りの生徒と 揃ってないとか、何だかんだと難癖をつけては、「高山、ふざけとる。運動場 3周!」とくる。
何ですと?一体誰が授業中に「ふざけている」というのですか。全く、小 学校の担任教師じゃああるまいに、人を不良呼ばわりするような言いがかりはやめ ていただきたいものです。私は今、全身全霊をかけてラジオ体操に取り組んで おります。ただ、周りの生徒の動きに合わせる余裕が無いだけです。 貴方がたは、生徒が全力で取り組んでいるか、ふざけてテキトーにやっているか の区別もつかないのですか。それでは、数学者になる日を夢みて丸一週間掛けて 準備したゼミの発表が期待される水準に達しなかった学生に、「ヤル気が無いな ら、数学なんかやめてしまいなさい!」と怒鳴り散らす数学者と変わらない のではないでしょうか。否、数学者の場合、ヤル気が無いと決め付けているの ではないことに注意すべきでしょう。ちゃんと「ヤル気が無いなら」とい う条件文を使っています。いいですか?「ヤル気が無いなら」というのは、 「ヤル気が無い。だから」ではなく、「もしヤル気が無いという前提条件が 満たされるならば」という意味ですよ。世間では条件文が正しく使われない場面が 多々みられますが、この点では数学者は職業柄いくぶん論理的なのでしょう。 しかるに貴方がた体育教師はどうですか。いきなり「高山、ふざけとる」と 断定形ですね。そうじゃないですね。「高山、(君が、もし)ふざけているのな ら、運動場3周!」が正しいのではないでしょうか、と。
勿論中学高校時代の私がこんな減らず口を叩けたわけではなく、体育の授
業の度に「冤罪事件」が発生し、他の生徒よりも沢山運動場走らされたり、
腕立て伏せやらされたりしたわけだ。でも、それで結構基礎体力ついたから、
「ま、いっか」って話もあるけどね。
2009年6月24日(水)
<<心の深層をえぐる>>
研究日。昼過ぎから京大へ。北部生協喫茶ほくとで昼食の後、理学部数学教室
の図書室へ。以前に分かったと思ったことが間違いだったことを発見した以外
は、さしたる進展はなし。16時半から17時半まで、同じ建物の大会議室で
代数幾何学の談話会。専門が遠いのでチンプンカンプンかと心配したが、案外
分かりやすくて面白い話だった。会場に居るのはほとんど京大系の代数幾何学
者。彼らは私が誰だか知らないはずなので、透明人間モードで漂っているのだ
が、「こいつ、最近よく見掛ける顔だけど、誰やねん?」みたいな視線をちらっ
と送ってくる人も居る。いいから、いいから、私のことなど気にしないでよろ
しい。談話会の後は、ラクト山科で饅頭を買って帰宅。
夜は、高校のOB・OG会 関連のメールのやりとりの後、少し数学。「高山くんって、立命館BKCで働い てるんでしょ?」「うん、まあ、ただ単に雇われているだけで、仕事はほとん ど自宅や街や夢の中でやってるけど」などなど。
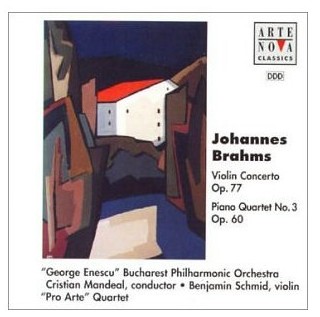 さて、今日の1枚は、何時買ったのか覚えてないけれど、最近私の部屋で「発
掘」された、ブラームスの「ヴァイオリン協奏曲二長調Op.77」と「ピアノ四
重奏第3番ハ短調Op.60」。演奏者はよく知らない人たち。ヴァイオリンの
Benjamin Schmidはちょっと有名人らしいけど、誰かに似ているなと思ったら
麒麟の川島明にそっくりだ。あと、ヴァイオリン協奏曲の方は、ときどき聴い
たことのあるメロディーが出てきて、何だったけ?としばし頭を抱えて考えて
みたところ、マーラーの「大地の歌」で使われていたと判明した。バロッ
クの頃だと結構こういうことがあるけど、ロマン派の時代でもメロディーの無
断(?)借用があったのかしらね。
さて、今日の1枚は、何時買ったのか覚えてないけれど、最近私の部屋で「発
掘」された、ブラームスの「ヴァイオリン協奏曲二長調Op.77」と「ピアノ四
重奏第3番ハ短調Op.60」。演奏者はよく知らない人たち。ヴァイオリンの
Benjamin Schmidはちょっと有名人らしいけど、誰かに似ているなと思ったら
麒麟の川島明にそっくりだ。あと、ヴァイオリン協奏曲の方は、ときどき聴い
たことのあるメロディーが出てきて、何だったけ?としばし頭を抱えて考えて
みたところ、マーラーの「大地の歌」で使われていたと判明した。バロッ
クの頃だと結構こういうことがあるけど、ロマン派の時代でもメロディーの無
断(?)借用があったのかしらね。
それにしてもブラームスの音楽って、相変 わらず切羽詰ってますねえ。こういうのも、結構いいかも。
ジャケットの絵もまずまずいい感じだ。誰が描いてるのか知らないけど、 ARTE NOVA classics のCDはこの手の絵が多く、「素晴らしい!」とまでは言 わないけど、結構いい線行ってるのが多いと思う。
でも、この絵、じいーっと見てると、全体の雰囲気が、あの口が×印の兎
ミフィーちゃんを彷彿とさせるんだよね。昔、ある職場でミフィーちゃんが大好
きな同僚と大喧嘩して、やっぱりハローキティー派の私としてはミフィー
的なものは受け入れ難いのだと、しみじみと思ったものだ。しかし、さらにじ
いーっと見ていると、赤い屋根の家が(いくぶんミフィー化した)口無し猫の
ハローキティーに見えなくもない。私の心の深層をえぐる不思議な絵だ。
2009年6月23日(火)
<<総合評価>>
ラクト山科で昼食用のパンを買って、昼過ぎに出勤。急いで昼食を済ませ、1
3時より14時半まで、経済学部・経営学部のC言語プログラミングの演習。
受講生はいつもの元気な2回生3人組。4回生の一人はとうとう来なくなっ
た。就職活動のためだろうか。ひきつづき、14時40分から16時10分ま
で、数理科学科2回生の代数の講義。皆さん、こっち向いて静かに聞いてくれ
てるけど、分かってるのかしら。講義の後、16時半から18時前まで教授会。
前半は睡魔の襲われ気絶していたが、後半はヨーロッパ数学会から依頼された論
文レビュー(その4)に着手。会議の後、生協で夕食をとって、研究室に戻っ
て来週の講義の準備を少ししてから帰宅。帰宅途中のバスと電車の中で、後期
試験問題を作り、帰宅後、TeXで打ち込んで完成。
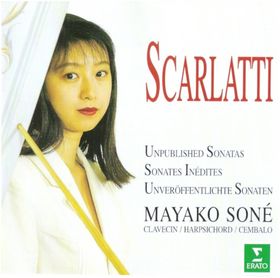 さて、今日の1枚は、曽根麻矢子が若い頃に出した「スカルラッティー未発表
ソナタ集」。チェンバロの音はピアノよりも個人差が大きいような気がするの
だけど、曽根さんのチェンバロは明るい音が魅力。特にスカルラッティーに
はよく似合っている。
さて、今日の1枚は、曽根麻矢子が若い頃に出した「スカルラッティー未発表
ソナタ集」。チェンバロの音はピアノよりも個人差が大きいような気がするの
だけど、曽根さんのチェンバロは明るい音が魅力。特にスカルラッティーに
はよく似合っている。
CDの中身は良いのだけど、このジャケットはどうよ?白の背景に白いスー ツ着て、何だか物陰からこちらを見ている図って、忍法変化の術で身を隠して いるくノ一ですか?この「物陰」は何だろう?ってずっと疑問に思っていたの だが、どうやらチェンバロの一部で、曽根さんの胸元を横切る白木の棒は、チェ ンバロの蓋を支えるつっかえ棒のようである。 私はてっきり、小太鼓を叩くス ティックか何かだと思ってて、へえ、曽根さんが何で太鼓なんだろう?まあ、 そういうこともあるのかしらって不思議に思っていた。
小学校5、6年生の頃に、クラブ活動と奉仕活動というのがあり、全ての 生徒はそれぞれいずれかクラブ活動と奉仕活動に入って活動することになって いた。花形クラブは鼓笛隊で運動会の行進で皆の前で演奏するのがカッコ良く、 特に男の子の間では小太鼓が人気だった。鼓笛隊に入っている5、6年生の男 の子が持ち歩く小太鼓のスティックは、私にとってはまさに憧れの象徴だった のである。
いっぽう、奉仕活動の花形は放送部で、昼休みに校内放送でクラシック音 楽を流したり、簡単なアナウンスをしたりということをするのだが、学校の放 送施設の機材を使ったり、防音室でマイクを前にしたりと、これまたカッコ良 かった。授業中に消しゴムを投げ合って先生に叱られたり、休み時間に運動場 で喧嘩ばかりしている一般の小学生に比べて、ワンランク上の人達というイメ ージで見ていたように思う。自分も放送部の人達の仲間になってハイブロウな 世界にのし上がりたい、という風に考えていたようだ。
5年生に上がる頃に希望調査と配属があり、選考と配属決定は担任教師達 が「諸般の観点から総合的に」行うのだが、花形クラブと花形奉仕活動は教師 達からの評価が高い品行方正な優等生でなければ採用されない。私は勿論、鼓 笛隊と放送部を希望し、自分なりに色々担任教師にアピールした積もりだった けど、結局、工作クラブと体育部に配属された。日頃から勉強には熱が入らず、 悪戯ばかりしていたことが災いしたようであるが、私より勉強が嫌いな、その くせ何事にも要領が良く運動神経抜群の悪党兄弟がいて、彼らが鼓笛隊に配属 されたのは、特に不満だった。要領の良さと運動神経が鼓笛隊と何の関係があ るのか?音楽の成績で多少差がついていたかも知れないが、楽器を演奏したり メロディーを聴き取ったりすることにかけては、私だって、そう捨てたもんじ ゃないぞ、と。
工作クラブも不満だった。私はモノ作りには全く興味の無い人間なので退 屈のひとことだったし、せめて絵が描ける美術クラブみたいなものにして欲し いと思ったものだ。おまけに担当教師にクラブの部長に指名され、副部長はこ れまた優柔不断の塊みたいな男で、「二人で相談してクラブのメンバーを纏め ていきなさい」と放り出されたのには往生した。副部長と相談しようにも、奴 は愚図愚図愚図愚図と要領の得ないことばかり言ってて、てんでラチがあかない し、担当教師も多忙を理由に教室に顔も出さずにほったらかし状態だった。 体育部の方も、体育倉庫のマットや跳び箱の整理ばかりで、体育の授業が嫌い な私にとっては、これまた往生した。下積み生活ってやつね。
6年生に上がる時にも再配属があるので、そのチャンスに賭けるべく、5 年生の時は勉強にも真面目に取り組み、廊下を走り回ったり友達と喧嘩するのも なるべく控えるようにした。しかし結局、奉仕活動は生活部。これは、例えば、 廊下を走っている生徒に指導・注意し、それに従わなければ先生に報告する権限 を持つ立場。体育倉庫の整理整頓よりはカッコいいかも知れないが、担任教師の 「他人を指導する立場になれば、自分の生活態度も改善するだろうと判断した」 という配属理由がどうも気に入らなかった。いつまでも人を不良扱いするな、と。 クラブ活動の方は何処に配属されたのか覚えていないが、鼓笛隊ではなかった。
かくして私は、中学に上がる頃には既に、上司の気まぐれな「総合評価」
に一喜一憂する人生だけは避けたいものだとの思いが骨の髄まで沁みていたの
である。忌まわしい記憶だけど、このジャケットの紛らわしいチェンバロのつ
っかえ棒を見なければ、こんな昔のことなど忘れてたのにね。写真の中の曽根
さんも、放送部に配属されるようなオリコーサンの女の子みたいな顔してるし。
まったく踏んだり蹴ったりのジャケットだよ。
2009年6月22日(月)
<<異様な緊迫感>>
梅雨時の蒸し暑い一日。ラクト山科で昼食用のパンを買って、昼過ぎに出勤。
事務で郵便物の確認、研究室こそこそ昼食の後、明日の授業のプリントのコピー
など。14時半より16時過ぎまで卒研ゼミA(可換環論・代数幾何学)。代
数幾何学をやっている方の学生の調子がどうも良くなく、テキストが合わない
ようだから変えてみようという話になった。本人はザリスキーやグロタンディッ
クなどの抽象的な議論が好きそうなのだが、代数幾何学の由緒正しい古典的話
題の方が君に会ってるかもしれないし、スキームとか層とかは単なる道具だか
ら研究者になろうと思った時に勉強すればいいよ、と。数学としては古典的話
題の方がうんと深いわけだし、実は私もそちらの方を一度勉強したいと思って
いたので。
ひきつづき卒研ゼミB(初等整数論)。教育実習組も帰ってきて、今日は 民間企業就職活動組を除いて全員顔を揃えた。今日は前回の宿題について私が 延々と講義して終る。丁寧に講義したら1コマ分の時間がかかる証明をたった 2行で書いているテキストってのも、なかなか凄い。それにしても、ゼミBは 生真面目学生揃いで、いつも異様な緊迫感に溢れている。去年は結構ボケをぶ ちかましてくれる学生が居て愉快だったのだが。
18時に終了して、すぐに帰宅。夜も少し数学。
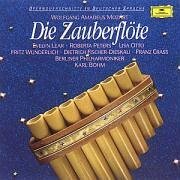 さて、今日の1枚は、カール・ベームが指揮するベルリン・フィルの「魔笛
(Die Zauberflöte)」。魔笛に限らず、オペラの曲はクラリネットなどの
室内楽としてよく演奏されているが、このCDは実際のオペラで演じるのと同
じように、全部歌になっている。
さて、今日の1枚は、カール・ベームが指揮するベルリン・フィルの「魔笛
(Die Zauberflöte)」。魔笛に限らず、オペラの曲はクラリネットなどの
室内楽としてよく演奏されているが、このCDは実際のオペラで演じるのと同
じように、全部歌になっている。
このCDは、2004年にエッセンに滞在した折、大家さんの奥さんから 頂いたもの。ちょうどエッセンが全ドイツに誇るオペラハウスで「魔笛」をやっ ていたので、エッセン大学のHerzog先生に連れていってもらったのだが、下宿 に戻ってきて「オペラ、良かったです!」とか話していたら、それなら、とい うことでプレゼントしてくれたのだ。
当時の私はまだモーツァルト嫌いで、Herzog先生にも「私に言わせれば、 モーツァルトなんてのはただただ美しいだけで、それがかえって嫌味で嫌いだ けど、オペラは初めてで面白そうだから試しに一度見てみたい」というような 事を(英語で)話していたのだが、ドイツ語しか通じない大家さんに「オペラー は面白かったが、モーツァルトは嫌いだからこのCDは nein danke ね」など と憎まれ口を叩く語学力が無かったので、何となく "Danke sehr! Sie sind immer wirklich nett!" (いつもご親切にありがとうございます)みたいなテ キトーな事を言って貰ってしまった。まあ、語学力が無いことも、かえって良 いこともあるのだ。このCDもずうっと聴かずに放置されていたのだが、今と なっては、良いものを頂いたと思う。
ジャケットの絵は、夏の琵琶湖の夜空を彩る連発式花火の仕掛け、、、な
んてことは勿論なく、鳥売り男のパパゲーノが使っている鳥笛である。
2009年6月21日(日)
<<アンパンマン?>>
研究日。昼間は近所のスーパーに買い物に出た以外は、論文レビューの仕事
(その3)。夕方近くには片付き、レビュー原稿をメールで送信。残りあと一
つだが、それが50ページ以上の大論文で、しかも最近はその方面にあまり興
味が無くなった分野のものだから、少し気が重い。まあ、6月中には片付けよ
うと思っているけど。
引き続き、火曜日の代数の講義の準備を終えたところで夕食の時間。夜は 夕涼みがてらに近所に買い物に出てから、また少し数学。
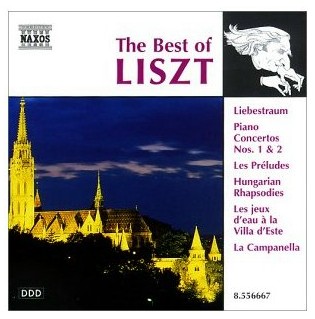 さて、今日の1枚は、The Best of LISZT. 「ハンガリー狂詩曲(2番と6
番)」、「ラ・カンパネラ」、「愛の夢」、「エステ荘の噴水」、「交響詩前
奏曲」、「ピアノ協奏曲(1番変ホ長調と2番イ長調)」と、フランツ・リス
トの有名な曲をいくつか集めたもの。演奏者も、NAXOS廉価良盤のシューベル
トのピアノ曲でお馴染みのイェノ・ヤンドー(Jeno Jando)を始め、色々なピ
アニストや交響楽団の録音を使っている。6月18日で紹介した「シェフお勧
め、J.S.バッハ各種盛り合わせ定食」と同じで、今ならこういうCDは買
わないけど、数年前に「リストって、どうよ?」と調査研究の一貫としてお試
しでこのCDを買ってみたのである。その後も超絶技巧ナントカというピアノ
の曲を聴いてみたり、色々やってみたのだが、リストはもひとつ趣味が合わない。
さて、今日の1枚は、The Best of LISZT. 「ハンガリー狂詩曲(2番と6
番)」、「ラ・カンパネラ」、「愛の夢」、「エステ荘の噴水」、「交響詩前
奏曲」、「ピアノ協奏曲(1番変ホ長調と2番イ長調)」と、フランツ・リス
トの有名な曲をいくつか集めたもの。演奏者も、NAXOS廉価良盤のシューベル
トのピアノ曲でお馴染みのイェノ・ヤンドー(Jeno Jando)を始め、色々なピ
アニストや交響楽団の録音を使っている。6月18日で紹介した「シェフお勧
め、J.S.バッハ各種盛り合わせ定食」と同じで、今ならこういうCDは買
わないけど、数年前に「リストって、どうよ?」と調査研究の一貫としてお試
しでこのCDを買ってみたのである。その後も超絶技巧ナントカというピアノ
の曲を聴いてみたり、色々やってみたのだが、リストはもひとつ趣味が合わない。
ジャケットのライトアップされた建物は、ハンガリーの首都ブダペストの Fisherbastion とかいう建物で、昔は魚屋ギルドの本拠地として市が開かれた りしていた有名な景勝地なのだそうだ。こういう夕闇の空に突き刺さる尖った 塔というのは、狂気にも似たものを感じさせる、いかにもヨーロッパっぽい風 景だ。右上の晩年のリストの似顔絵とこの風景が実によく似合っていることは、 仮にリストの代わりにアンパンマンの絵を入れてみたらどうなるかを考えてみ るまでもなく分かる、、、はず?
若い頃のリストの肖像画を見ると、まさに元祖イケ面アーティストって感
じ。その上、ちょっとニヒルな感じでピアノが抜群に旨いとなれば、女性達の
間に熱狂的ファンが多かったというのも、さもありなんと思う。
2009年6月20日(土)
<<自棄になることはありません>>
ドイツ語の日。午前中はインターネットでドイツ語のテレビ放送を見て、
それからマックス・プランク研究所のホームページを冷やかしていたら、
凄い記述があったので、引用する:
"Um die Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, benotigen Sie eine Arbeitsgenehmigung, es sei denn Sie werden von der Max-Planck-Gesellschaft als Wissenschaftler beschaftigt. Umgekehrt benotigen Sie fur die Arbeitsgenehmigung eine Aufenthaltsgenehmigung. (Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Das Problem ist in der Praxis losbar.)"
「(ドイツ国内の)滞在許可を得るためには、マックス・プランク財団に科 学者として働くことの労働許可が必要です。逆に、労働許可を得るためには、 滞在許可が必要となります。(このことで自棄(ヤケ)になることはありませ ん。この問題は実務の中で解決可能です。)」
役所に滞在許可を貰いに行ったら、3時間待たされた挙句、別の役所で労 働許可を貰って来いと書類不備で門前払いを喰らい、次の日に労働許可を貰 うために別の役所に出向き、これまた3時間待たされた挙句、滞在許可がでて ないから駄目だと突き返される。こういうことはドイツではいかにもありそう だ。私が経験したのは、滞在許可の延長手続きに必要な書類が、対応する事務 職員(すべて同じオフィスに居る人達である!)によって少しずつ違っており、 対応した事務職員の数だけ「出直して3時間待ち」を繰り返さなければならな い、というのがあった。
それにしても「自棄を起こさなくても、ちゃんとやり様はある」と公式ホ ームページに書いてあるところがドイツの恐ろしいところだと思う。「君たち が馬鹿でないのなら、『実務の中で解決する』のではなく、論理的に解決した らどうなのかね」と言いたいものだ。
京大ルネで遅めの昼食の後、関西日仏学館の図書室で少し予習をしてから 寺子屋へ。授業の後、また関西日仏学館で1時間ほど勉強してから、再び寺子 屋へ。ここはドイツ料理店もやっていて、今日は近所の人や講座の受講生が集 まって夕食会。こういう機会だけ顔を会わせる他クラスの人なども交えて、上 記マックス・プランク財団のHPの話などで盛り上がり、21時前に退散。
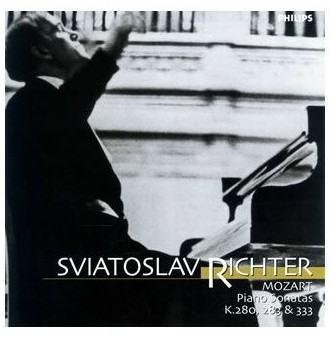 さて、今日の1枚は、スヴャトスラフ・リヒテルのモーツァルト「ピアノ・ソ
ナタ第2、5、13番」。しっかりした全体構成の上にひとつひとつの音がゆ
るぎなく、つけいる隙を与えないモーツァルト。とても綺麗だけど、長く聴い
ているとちょっとしんどい。しかし、最後に弾いている第5番の第3楽章は、
その疲れを吹き飛ばしてくれるような、軽快で胸のすくような演奏。
さて、今日の1枚は、スヴャトスラフ・リヒテルのモーツァルト「ピアノ・ソ
ナタ第2、5、13番」。しっかりした全体構成の上にひとつひとつの音がゆ
るぎなく、つけいる隙を与えないモーツァルト。とても綺麗だけど、長く聴い
ているとちょっとしんどい。しかし、最後に弾いている第5番の第3楽章は、
その疲れを吹き飛ばしてくれるような、軽快で胸のすくような演奏。
それにしても、1966年のザルツブルクでのコンサー トで録音されたものらしいが、聴衆(たぶん同一人物)が咳をしたり鼻をすすっ たりする音が結構うるさく、それがいつまでも続いているところが気になる。
コンサート会場で、演奏中に音を立てたり不穏な動きをする観客への対応 は、会場の管理責任者にとって頭の痛い問題のようで、休憩時間などにスタッ フらしき人達がフロアの隅に集まって、何列の何番目のお客様の○○には他の お客様からの苦情も出始めています、従ってコンサート後半での対応としては こうしてああして云々と打ち合わせをしていることもある。
このジャケットは私のお気に入りの一つである。演奏者の上空に広
がる空間が心地よく示唆されていて、カメラのアングルも意外性とともに
鋭い臨場感がある。
そして最も気に入っているところは、右下の"Richter"の白抜き文字とその背
景の黄土色の帯。モノクロの絵に、控えめだけど素晴らしいアクセントになっている。
2009年6月19日(金)
<<午後はどこも閉館>>
研究日&関西日仏学館の日。午前中は自宅で野暮用。昼過ぎに京大へ。生協喫
茶ほくとで昼食をとり、少しフランス語を勉強してから、数学教室の図書館へ。
と、「本日午後は臨時休館」だと。昨日は創立記念日で休み、そして今日は午
前中だけ少し開けて、午後は何か知らんけど休み、そのまま週末休館に突入。
一体何の真似だ?
しょうがないので、関西日仏学館の図書室へ。先日の「重大な勘違い」の 件について詳細に検討。なるほど、あることが証明できたと思ったけれど、実 はまだまだ遠い道のりであることが明らかになった。
15時半頃、トイレのため図書室を出てまた戻ってきたら、事務員が「本 日は臨時に15時から18時まで図書室は閉館だ」と。嗚呼、関西日仏よ、お 前もか! 今日は京都市内の図書館員が示し合わせて一斉ストでもぶつ日なの かしら?ストをするなら事前に予告して欲しいものだ。京都新聞の朝刊で全面 広告を出すとか、NHKの朝のニュースでアナウンスしてもらうとか、半鐘を 打ち鳴らすとか、どんと空砲を撃ってみるとか、発炎筒を焚くとか、のろしを 上げるとか、花火を打ち上げるとか、伝書鳩を飛ばすとか、のぼり旗を立てて みるとか、提灯行列をしてみるとか、何なりとやりよう があろうに。こちらだって色々都合や段取りってものがあるんだぜ。
しょうがないので、中に置いてある荷物を取りに戻ったのだが、結局、そ の場に居た司書の人にも何も言われることなく、他の何名かの利用者とともに 夕方ごろまで勉強していられた。図書のカウンター業務をする人が居なくなっ ただけで、館内の本を閲覧したり勉強したりする分には構わないということら しかった。しかし夕方には京大ルネに移動し、フランス語の勉強をすこしやっ てから、少し早めの夕食。夜はフランス語の授業を受け、京都市役所前まで徒 歩、それから地下鉄で帰宅。路上飲酒はなし。
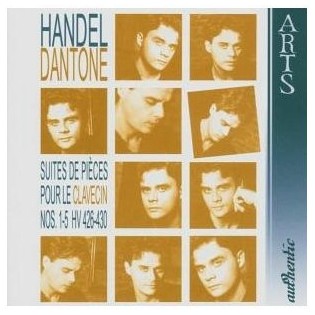 さて、今日の1枚は、オッタヴィオ・ダントーネのチェンバロで、ヘンデルの
「チェンバロ組曲集・第一集」。ヘンデルの室内楽は好きだけど、「水上の音
楽」などの管弦楽はどこが良いのか全然わからない。結局、ヘンデルの膨大な
作品群の中のごく一部をつまみ食いしてるような聴き方をしている。
さて、今日の1枚は、オッタヴィオ・ダントーネのチェンバロで、ヘンデルの
「チェンバロ組曲集・第一集」。ヘンデルの室内楽は好きだけど、「水上の音
楽」などの管弦楽はどこが良いのか全然わからない。結局、ヘンデルの膨大な
作品群の中のごく一部をつまみ食いしてるような聴き方をしている。
チェンバロも、弾き方の違いなのか、録音状態の違いなのか、CDによって ずいぶん音の違いがあり、どこかで名前を聞いたことのある有名な演奏家の古 い録音などを試聴してみたら、どうにも癇に障るような音だったということも ある。ピアノよりも音の個人差が激しい。その中でも、このCDのチェンバロ の音は私好み。
で、このジャケット。「ダントーネさん、貴方、グレン・グールドを意識 してますね。」セピア色の写真をいくつか並べるところなど、グレン・グール ドの1955年版「ゴールドベルク変奏曲」(モノラル版)のジャケットに ちょっと似ている。同じ鍵盤楽器の演奏家でイケ面同士だったりすると、こん なところで張り合うのか、というのは下衆の勘ぐりか。
でも私としては、この10枚の顔写真が全部ハロー・キティーだったら
良かったのになと思う。昔はイケ面が好きで、「イケ面に囲まれていると、
自分もイケ面になったような気分になれる」とか言って喜んでいたのだが、
オッサンになると、「そりゃあ、やっぱり、イケ面よりもハロー・キティー
でしょう!?」って気分になってくるものなんよ。
2009年6月18日(木)
<<世間の義理>>
研究日。午前中は昨夜から書いていた論文レビュー(その1)の仕上げをして
メールで送信。午後は京大へ。しかし行ってみると、大学の創立記念日とかで、
生協の一部を除いて閉まっていた。京大は相変わらず余裕かましてるな。創立
記念日も蹴飛ばしてガンガン授業しないと、文科省が指導する「15週授業の
鉄則」が守れない私大とは大違いだ。
しょうがないので、関西日仏学館の図書室へ。先日来の懸案2つを考えた り、論文レビュー(その2)の作業をしたり、昨日コピーしてきた論文を眺め たりしているうちに、夕方になる。懸案2つはようやく解決。レビュー(その 2)はほぼ目処が立った。
さあ帰ろうと、雷と激しい夕立の中、京都市役所前までバス。JEUGI A三条本店とAnger河原町三条本店を偵察してから、地下鉄にて帰宅。 夜は論文レビュー(その2)を仕上げ、メールで送信。
ヨーロッパ数学会のレビューの仕事は面倒になってきたから返上しようと 思っていたのだが、レビューを依頼されている論文の著者の一人に、ある事で 推薦状を依頼することになった。それ以外の論文の著者も何となく知ってる人 ばかり。それで世間の義理みたいなものを感じて、やっぱりちゃんとやろうと 思い直したのである。
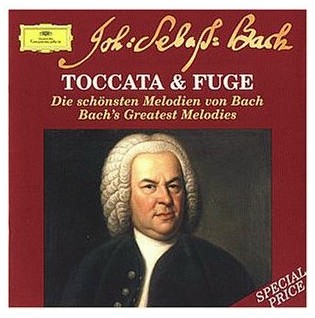 さて、今日の1枚は、J.S.バッハのトッカータとフーガを集めたもの。演
奏者は、どこかのオーケストラやテノール歌手、ピアニストと色々。2000
年か2004年かのいずれかにエッセンで買ったものだと思うけど、こういう
買い方をしてた時があったんだなと、我ながら感慨深い。今の私は、演奏者の
良し悪しで選ぶので、こういった「J.S.バッハ関連各種取り揃え」みたい
なCDには手を出さない。聴いてみた感想としても、「いい演奏もあったし、
特に感動しない演奏もあった」としか答えようがないのだ。
さて、今日の1枚は、J.S.バッハのトッカータとフーガを集めたもの。演
奏者は、どこかのオーケストラやテノール歌手、ピアニストと色々。2000
年か2004年かのいずれかにエッセンで買ったものだと思うけど、こういう
買い方をしてた時があったんだなと、我ながら感慨深い。今の私は、演奏者の
良し悪しで選ぶので、こういった「J.S.バッハ関連各種取り揃え」みたい
なCDには手を出さない。聴いてみた感想としても、「いい演奏もあったし、
特に感動しない演奏もあった」としか答えようがないのだ。
このバッハの肖像は、昔の小中学校の音楽室には必ず飾られており、私は この人体解剖模型の腸を思わせる髪型が大嫌いで、単にそれだけの理由でバッ ハが嫌いだった。このオッサン、何で腸を頭に被ってるんだ?おかしいやん! と。もっとも、これがカツラだと知ったのはごく最近のこと。当時の人は、水 が原因と信じられていた病気を避けるため、髪を短く切って洗髪を避け、普段 はカツラを被っていたそうだ。
カツラだとしても、この典型的オジサン顔に、このヘアスタイルと
なで肩は全然似合ってないと思うので、もうちょっと何とかならなかった
のかなと、いつも思うのだ。当時はこういうのが流行ってて、この
オジサン顔も、実は「どうだ、オレ、カッコいいだろ?」って澄ましてる
のかも知れないけどね。
2009年6月17日(水)
<<重大な勘違い>>
研究日。午後は京大へ。耐震補強工事のため、京大数理研の図書室は来年3月
一杯まで閉鎖されてしまった。そこで理学部数学教室の図書室に行ってみた。
この建物も割合最近耐震補強工事と大幅なリフォームが行われ、新しい図書室
に行くのは今日が初めて。色々文献検索をして論文を3つほどコピーする。
16時半から1時間ほど、数理研で談話会。今日は高次元類体論の話。類体論の
何たるかから最新の研究動向まで、とても分かりやすい良い話だった。
夜 は先日ヨーロッパ数学会から督促が来ていた論文レビューの仕事に着手。途中、 逃避行動として研究関連であちこちにメールを出しまくる。
最近、ある定理が証明できそうな気がしていて、「でも、何か重大な勘違 いをしているような気がします」と某先生にメールを出したら、すぐに返事が 返ってきて、やはり重大な勘違いをしているようだと分かった。ちょっとメー ルで聞いてみて、すぐに有益なコメントが返ってくるというのは、とても有り 難い。
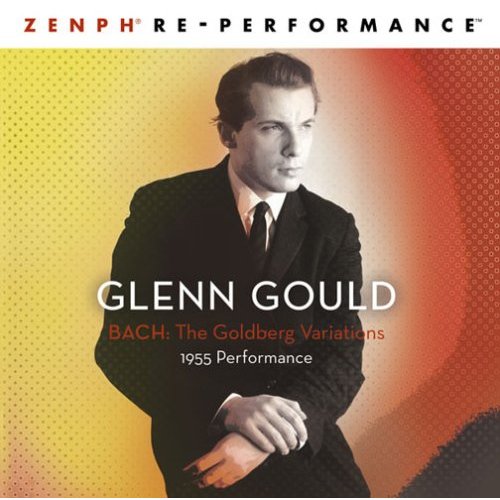 さて、今日の1枚は、グレン・グールドの「ゴールドベルク変奏曲」の195
5年録音盤(モノラル録音)をコンピュータで詳細に分析してデジタルデータ化
し、そのデータを自動演奏ピアノに食わせて1955年当時のグールドの演奏
を再現し、それを録音してできたCD、というかなりややこしい代物。流石に
演奏中のグールドのハミングまでは再現してないし、結局ニセモノじゃん!と
いうグールド・ファンの怒号が聞こえてきそうである。でも、私はモノラル録
音というだけの理由でホロヴィッツの古い録音をパスする人間なので、
「音が良ければ、そっちの方がいいじゃん」というノリで買ってしまった。
ま、別に後悔はしてませんけど。
さて、今日の1枚は、グレン・グールドの「ゴールドベルク変奏曲」の195
5年録音盤(モノラル録音)をコンピュータで詳細に分析してデジタルデータ化
し、そのデータを自動演奏ピアノに食わせて1955年当時のグールドの演奏
を再現し、それを録音してできたCD、というかなりややこしい代物。流石に
演奏中のグールドのハミングまでは再現してないし、結局ニセモノじゃん!と
いうグールド・ファンの怒号が聞こえてきそうである。でも、私はモノラル録
音というだけの理由でホロヴィッツの古い録音をパスする人間なので、
「音が良ければ、そっちの方がいいじゃん」というノリで買ってしまった。
ま、別に後悔はしてませんけど。
1955年といえば、私はまだ生まれてなかったけど、23歳ぐらいの グールドの髪型やスーツの形は、いかにも1950年代の北米大陸って感じが して悪くない。ただ、そこはかとなく投げやりに描かれたような 背景は、図らずしもサーモグラフィで映し出されたグールドの熱いオーラ みたいに見えて、ちょっと妙な感じだ。
私:「タイトなスーツでびしっと決めて、暑いの無理しとるんとちゃうの?」
グールド:「ふっ、そんな事はないさ。でも、ピアノ弾きすぎて左の手首がちょっと 痛いんだ。」
私:「何にしても、あんまり無視したら、あかんよ。」
この写真のぴんぴんの若っかい兄ちゃんが、25年ぐらいすると5月7日
に紹介した陰鬱な目をしたオジサンになって、「おい、幸坊!」とか
話しかけてくるんだぜ。
2009年6月16日(火)
<< 代数は美しい! >>
ラクト山科で昼食用のパンを買って、昼頃に出勤。研究室こそこそ昼食の後、
13時より14時半まで、経済学部、経営学部のC言語プログラミング演習。
今日の出席者は、いつも元気な2回生の男の子3人組。今日は質問も少なく比
較的暇だったので、学生の監視をしながら昨日の卒研ゼミで懸案になっていた
問題を解く。
教室を移動して、14時40分より2回生の代数の講義。講義のあと、学 生たちが「代数は美しい!」と呻いていた。これが美の伝道師を密かに自認す る私の講義の効果ならば、大変喜ばしいのだが。
講義の後、来週の授業のためのプリントをコピーしたりしたあと、山科の スーパーに寄り道して買い物をしてから帰宅。夜は少し数学。先日来さっ ぱり分からなかった事が、すこし分かった。
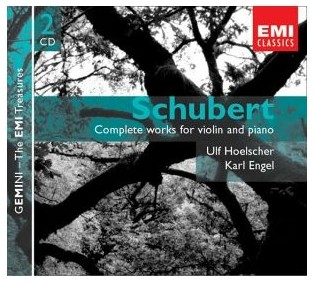 さて、今日の1枚は、UlfHoelscher (ヴァイオリン)と
Karl Engel (ピアノ)による2枚組CDで、シュー
ベルトの「ヴァイオリンのための幻想曲・ハ長調D934」「ヴァイオリンの
ためのロンド・ロ短調D895]「ヴァイオリンソナタ・二長調D384」
「ヴァイオリンソナタ・イ短調D385]「ヴァイオリンソナタ・ト短調D4
08」「ヴァイオリンソナタ・イ長調D574」。
さて、今日の1枚は、UlfHoelscher (ヴァイオリン)と
Karl Engel (ピアノ)による2枚組CDで、シュー
ベルトの「ヴァイオリンのための幻想曲・ハ長調D934」「ヴァイオリンの
ためのロンド・ロ短調D895]「ヴァイオリンソナタ・二長調D384」
「ヴァイオリンソナタ・イ短調D385]「ヴァイオリンソナタ・ト短調D4
08」「ヴァイオリンソナタ・イ長調D574」。
これもエッセンで買ったのだけど、ここ2、3年聴いてなかった。ヴァイ オリンの甲高い音が苦手な私としては、えいっ!やっ!っと少し勢いをつけな いと聴く気になれないけれど、いざ聴いてみるとシューベルトらしい瑞々しい 感性溢れる良い演奏だと思う。
ジャケットの写真は、森の樹を見上げたところ。この光乏しい陰鬱なモノ
クロといい、微妙にひねくれたぶっとい樹の幹といい、もうドイツ・オース
トリア的雰囲気ムンムンじゃあありませんか。"Schubert" の文字や演奏者の
名前などが書かれた半透明ブルーの帯と右上の赤いEMI classics のロゴのコ
ントラスも鮮やか。